| |
|
リフォーム事業の「責任者」はワンマンでなければならない
|
|
リフォームに限らず、新しい事業が軌道に乗るまでの間はいわゆる「起業家精神」がどうしても必要です。特に下請けから元請事業を展開したり、大手企業が新規事業としてリフォーム事業に取り組む場合には責任者の「起業家精神」が成功を左右するもっとも大きい鍵になるといっても過言ではありません。
特にリフォーム事業をはじめた当初は目指すべき姿と現実のギャップに大きな舵取りが必要なこともしばしばです。ビジネスモデルを作り上げる創業過程において、壊して創る、壊して創るのドラステックな試行錯誤の繰り返しが成功にもっとも近い道なのは皆様が感じられている通りです。そしてそれにはスピードが必須要件です。このため大手企業などが新規事業としてリフォーム事業を起こす場合は責任者によほど大きな権限が与えられていない限り成功するのは難しいというのが実感です。
もちろんついていく社員にとってはたいへんです。社員の大規模な入れ替わりなども成功したリフォーム経営者のほとんどが経験済でしょう。このような事態に即応し、「起業家精神」を存分に発揮するために、「ワンマン」体制は不可欠の要素です。「ワンマン」という言葉に語弊があるときは「強烈なリーダーシップ」といっても良いと思います。
私はリフォームの事業は年商5億程度まではワンマン経営でよいと思います。責任者がスタッフの誰からも認められるだけの、高い目標と熱意を持ち続け、リフォーム事業にかかわる勉強や努力を日々怠っていなければワンマン経営で何ら問題はありません。スタッフの誰よりも熱心に事業に取り組んでいればそれはおのずと社員に伝わるものです。スタッフから「ワンマン体質」だとか「朝令暮改」とか批判されることにいちいち反応しなくても良いでしょう。
むしろ怖いのはワンマン体制でないことによる「意思決定の遅れ」です。特にビジネスモデルの模索・構築期において「意思決定の遅れ」「スピード不足」はただちに「試行錯誤」の停滞につながります。
例えばイベントひとつをとってみても、実際にやってみなければ効果はわかりませんし、もちろん効果を保証できません。そのために30万円の出費が必要で決裁や実施そのものに時間がかかるようですと長い目で見て無駄な時間が流れます。
失敗してもその失敗から金額以上のノウハウを取得できるか否かが成功と失敗を本当に分けるといわれています。「意思決定の遅れ」によりノウハウやビジネスモデル習得に多大な時間を浪費してしまい、企業の気力や体力にも大きな影響を及ぼす事例を私は数多く真直に見てきました。リフォーム事業を新築の延長ととらえた多くの企業がこの壁にぶつかり撤退を余儀なくされてきました。
多少強引な手法とるにしろこの壁を乗り越えて道筋をつけるワンマン経営者もやはり数多く存在します。しかしどんな企業でも成長を続けていけばある程度の規模を境に、幹部や右腕に権限委譲を進めていく時期がやってきます。その時期をこえるとそれ以上の成長を求める社長は現場を離れ、経営戦略や多角化経営などの大きな流れに舵取りをする役目を担うことが多いようです。
ただしこの段階でワンマンゆえに生じる様々な問題よりも、ワンマンではないために結局失敗するケースも多いのが実態です。
ちなみにワンマン経営でなく、経営上の判断をするときにまで、社員みんなの意見をよく聞くということはよくあります。経営者がスタッフのモチベーションアップや経営哲学からボトムアップの手法を取られている場合はよいと思いますが、勉強不足だったり、自信がない、責任を一人で負いたくないなどからくる停滞は避けなければなりません。経営者と社員では目指すものが同じではなく、むしろ背反することも多く、経営判断の遅れや変革への対応の遅れにつながり、結果として成功の足かせになる場合は多いようです。
比較的大きな企業がリフォーム事業をはじめる場合は、経営者がリフォーム事業の責任者(店長など)にほとんど権限を与えないケースもよくあります。経営者が現場責任者に権限を与えずに責任だけ押し付けることはどうしても避けなければなりません。本業経営者や本業社員との意識の違いによる軋轢や妨害などによる熱意の低下もかなり多いです。 |
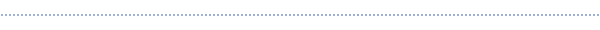 |
スタッフが技術者集団になったら高い成長を維持することは難しい
|
|
リフォーム事業の成否を握るのは多くの場合、「顧客開拓力」に直結するマーケティング、営業力そのものや「工事」「デザイン」などの技術力でもありません。社内や組織などの会社の内側で「攻めの形」が造れず、時間の経過とともに経営体力や意欲が失われて内部崩壊してしまうことが多いからです。
例えばよくある例として総合リフォームやクレームのない工事を目指す時に店長に建築士などの技術者を据えることで、売上が伸び悩むことが多いのは事実です。建築士はもともと技術屋ですから専門職としてはいかにすばらしくても、営業面やマーケティング面に弱いのはあたりまえです(もちろん例外はあります)。専門化を進めるほど選択できる戦略の幅が狭まり成長率が鈍化するのは他の業界でもよく見られる現象です。
事実、技術者を営業の要職に配置することで、店全体が技術会社になってしまう例はきわまて多いのです。元請営業を意図したリフォーム会社のはずが,技術志向の工事会社になってしまうケースです。店全体に顧客を積極的に受け入れる活気が乏しくなり、ほとんどのスタッフが図面や見積に追われてしまい、お客様が来店しても顔さえ上げられなくなってしまいます。これでは高いレベルの工事や提案は可能かもしれませんが、元請リフォーム会社として最もエネルギーを注力すべき「顧客開拓」は難しいでしょう。
これに対し、営業マンが活気にあふれているリフォーム会社では技術担当者にも営業的な要素が自然に染み付いてきます。短期間で成長を遂げたリフォーム会社は大概、営業先行で技術後追いの形をバランスよくとっています。年商3~5億の規模を早期に突破した成功店に、このような成功パターンはよく見られます。
繰り返しますが、事業の立ち上がり時期に最初から大きな建築工事をターゲットにしたり、技術的な弱さをカバーしようとして技術者をスタッフとして採用してみたが、技術者の意見(考え方)が営業方針に必要以上に重用されることで、営業力が弱体化してしまうケースはかなり多いのです。
ただし例外もあります。きわめて強い販売力とリーダーシップをもつ責任者が営業面で集客などに全責任を負い、社員は設計士など技術者ばかりで社員には提案・施工面に特化させる手法です。 |
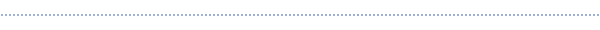 |
数字やデータ管理に弱いリフォーム経営者が大きく成長することは難しい
|
|
リフォーム事業の特質として「新築と比較して扱う現場数(顧客数)が格段に多い」「大きい現場から小さい現場まで工事が千差万別で標準化や管理が難しい」「新築と違い物件単価が低いため、粗利益率を管理しなければ儲からない」等の点が上げられます。
A社は年商5億規模ですが年間に2000現場超をこなしていますので、経営者がすべての現場の数値を管理することは難しく、これを統合管理しなければ行き当たりばったりの危ない経営になることを恐れて年商の1~2%をITに投資しています。
これら膨大なデータを処理するために、弊社ソフトのようなリフォーム事業専用ソフトの市場は生まれました。数値やデータの管理を疎かにすることは、経営者として「木を見て森を見ない」ということになり、ミクロな視点で判断することが多くなり、経営判断を誤りがちです。市場の値引き競争の中で粗利益をベースにした顧客管理、売価管理、原価管理を実践するリフォーム企業のみが利益を生み出せる組織と体制、ノウハウを確立できるといわれています。
また実績を経営者やスタッフがリアルタイムに具体的な数字で確認し、共有することで、達成感が生まれ、次の目標への意欲が生まれます。またスタッフの粗利や平均単価など数値を分析することで本当の問題点が見えてきます。具体的には「現場が途切れずにあって朝から晩まで忙しいのにちっとも儲からない」「いままでの顧客数はかなりあるのにリピートがあまりない」などという非効率な経営に陥ってしまいます。
特にどうしても必要な機能は「顧客管理」「見積」「原価・粗利管理」の三点です。
①「顧客管理」についてリフォームの場合「リピート需要」が大きな割合を占めますので、「顧客管理」ソフトは最初から準備した方がよいと思います。長期的には「顧客の囲い込み」「生涯顧客化」のためにもつながります。リピートが少ない会社は単なるOBへのPR不足がほとんどです。お客様は最初小さな工事を依頼してみて工事業者の様子をうかがい、気に入った業者には追加工事やリピートで大きな工事を依頼することがよくあります。
②「見積」ソフトも必要です。提出した見積書はお客様の購買履歴ですから、アフターなどでお客様から問い合わせがあったときに、逆にお客様に品番を問合せるようなことはリフォーム会社として恥ずべきことです。またベテラン社員が苦労して蓄積した自社独自の見積ノウハウを、新入社員が有効活用することで見積提出のスピードアップが可能です。
③「原価・粗利管理」ソフトも必要です。リフォーム業界では粗利率の高い企業ほど儲かっているといわれています。リフォーム事業での安売り戦略はリフォーム経営を疲弊させる劇薬のようなものです。安売り戦略では過去に多くのリフォーム企業が立ち行かなくなっています。
現場単位の原価管理はマイクロソフトエクセルなどの表計算でも可能ですが、営業ごとの月単位の粗利管理などは専用ソフトが必要です。
弊社ソフト(リフォームサクセス)は顧客⇔見積書⇔工事台帳(粗利/原価管理)が互いにリンクされ、10台以上のPCで快適に同時使用が可能です。リフォームサクセス5を導入するだけで現場単位だけでなく担当別でも粗利益管理可能ですので、自然に社内に利益意識・原価意識が徹底していきます。また集計作業等を省力化、間接人件費(事務員など)が少なく、ムリ・ムラ・ムダのない効率経営が実現できます。 |
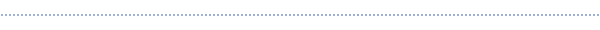 |
メーカーの提案を盲信しない。活用できないショールームに過大投資してはならない
|
|
地方の資金が潤沢な会社によくある例として、まず形からということでリフォーム事業開始時に特に住宅設備メーカー等の提案を受け入れ、ショールームに何千万も投資する経営者が以外に多いのですが、残念ながら大きな無駄遣いになることが多いようです。かかったコスト以上に成功しているケースはきわめてレアケースです(もちろん成功例もあります)。ショールームに数千万投資したものの、元もとれずに撤退した事例を私は何十回も目にしています。
ショールームで集客しようとかショールームで信用を勝ち得ようという「箱もの発想」そのものが安易な「待ち」の営業につながりやすいからです。また実際には小売店のように店舗運営そのもののノウハウがない会社がほとんどですから、ハコを作るのは得意でも結局活用ができないケースがほとんどです。
はじめは2階事務所でも十分です。ただ、打ち合わせ・応接スペースは相応に必要です。関東圏で数十店舗展開している大手チェーン店には店舗は打ち合わせスペースのみで1階不可(家賃が高いので)という不文律をもつ提案型リフォーム会社もあります。
ショールームが必要な場合はリフォーム相談会はもちろん。地域のイベントに場所を開放するなどの活用ノウハウがあり、イベント集客などを継続して行っていく場合です。
イベント集客のノウハウがあり、継続してショールーム集客の仕掛け作りが可能であれば大きな武器になると思いますので、レイアウト変更などが容易なスペース活用型ショールームはあってもよいと思います。ただし商品展示だけを目的としたショールームは往々にしてメンテナンスが行き届かず、逆効果になる可能性があります。 |
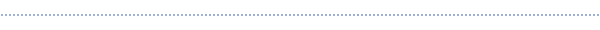 |
「粗利益率」と「平均単価」へのこだわりが成功の鍵を握る
|
|
元請リフォームの成功店の場合、スタッフ一人あたりの売上は3500~4500万/年です。スタッフ一人あたりの粗利益は90~130万/月位が目安となります。
リフォーム部門がうまくいっていない。つまり赤字事業の場合は「売上」以外にはまず「粗利益率」と「平均単価」に注目します。
「粗利益率」が低い場合は、新築が得意な会社のリフォーム部門に多く見うけられます。彼らは見積時に新築と同じ値入を行いますから当然粗利益は新築並となります。仕様が決まれば棟梁に任せられる新築と違い、一軒一軒現場状況もお客様も千差万別で経費がかかるリフォーム事業では、新築と同じアラリでやっていけないのはあたりまえです。新築と違ってリフォームは大変な手間と心配りが必要です。心配りが足りないとすぐにクレームになります。多くの町場の工務店が「リフォームは細かくて儲からない」と嘆くのはこのような特質を理解せずに新築のやり方をそのままリフォームにあてはめているからです。
成功店の「粗利益率」の適正値は新規顧客やリピートの多寡、もしくは戦略的な粗利設定にも左右されますが概ね30~36%位でしょう。少なくとも元請リフォーム会社で粗利益平均が25%以下で黒字体質を保つことはきわめて困難です。
「平均単価」もきわめて重要です。設備工事店のリフォーム部門などで平均単価が20万円台のケースがよくありますが、これは得意のトイレ工事の比率が圧倒的で、それ以外の部位提案に自信がないことが多くあります。これでは確かに専門分野に特化していますのでクレームは少ないかもしれませんが、たいがい提案力不足となり、平均単価は伸びませんので「朝から晩まで働いても忙しくて儲からない」魔のスパイラルにはまってしまいます。
総合リフォーム店では概ね60~70万円が営繕などの小工事を入れたすべての現場の平均単価です。「平均単価」は「粗利益率」と違い、営業が常に「平均単価」を意識し、自信を持って顧客に提案することで概ね解決することができますので、顧客からトイレを修理してほしいといわれて、トイレだけを直すのではなく、リフォーム時期に差し掛かった部位は積極的に追加工事や部位拡大提案の売込みする姿勢はプロとしてあたりまえの営業姿勢だと思います。 |
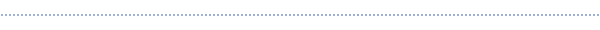 |
下請→元請化に成功するためには、跡取を責任者にして、別会社化が必勝パターン
|
|
地場の大手ゼネコンやサブコン、ビルダー、ガス会社などが本業不振のあおりで、メーカーのチェーンの看板を掲げてリフォーム市場に参入するケースが増えています。本業顧客の活用など相乗効果を当てにして安易に参入する場合もあると思います。私もメーカー出身ですのでこの辺の事情はよく承知していますが、このパターンで成功することはきわめて難しいと思います。
まず第一に本業経営者や幹部が過去の成功体験を元請事業にあてはめて考えている点です。下請け事業で成功したノウハウは残念ながら元請事業には当てはまらないようです。結果として現場責任者の店長などは上司の方針と現場のギャップに悩み、やる気を失ってしまいがちです。
次にうまくいかないケースは現場責任者を本業の営繕担当など人当たりがよい職人や設計士などに任せる場合があります。この場合も「その二」で提言したようにもともと技術者である人材にマーケティングや経営数値を背負わせることになり、人材や能力のミスマッチや弊害が生じがちです。
これらを解決するためにはサラリーマンよりも踏ん張りのきく「跡取」となるような人材を責任者に抜擢し、新会社を設立して本業とは別の場所で新たにはじめることです。本業との相乗効果がなくなってしまうと危惧する声もありますが、本業のネームバリューがなかったり、本業のバックアップがなければたちいかなくなるような組織であれば結局は本業のお荷物部門となってしまいますし、リフォーム事業の起業は跡取の修行の場としてはもってこいだと思います。
もちろん下請業から元請業に転進は決して簡単ではありません。成功店では多くの場合、別業界等に修行に出ていた息子を自分の会社に復帰させることでこの困難を乗り越えています。 |
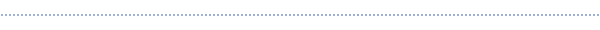 |
成長を左右する最も大きな要素「人を活かす」能力は経験だけでなく、学習である程度まで克服できる
|
|
あるリフォーム会社で長い間トップ営業だったA君が独立して、周囲は大変期待していたのですが、A君の新会社は思いのほか売上が伸びることはありませんでした。A君が採用する社員が次々と辞めてしまい、A君はすっかり疲れてしまいました。
トップ営業=優秀な経営者とは限りません。トップ営業マンは多くの場合短期的な人身掌握術には長けていますが、長期的に安定して良好な人間関係を築けるタイプはごくまれです。またトップ営業マンは短期間で顧客と信頼関係を築けるある種の「天才」ですから、たいていのことはその能力で乗り切ることができるため、その能力に頼ってしまい新たな知識の吸収などの勉強などをしたがらないタイプが多く、結果として経営者として大成しないタイプが多いようです。A君はいま初心に返って経営者としての勉強を続けています。
ご承知のようにリフォーム事業は営業の根幹を「ヒト」が担っています。ですから「優秀でまじめな人材」を多く抱え、共通の目標に向かって邁進することに成功した会社が強いのです。「人を活かす」ための経営能力も、販売やマーケティングと同様勉強や研修で能力は身につくと思います。そしてその能力を発揮する過程で組織をまとめるための「経営理念」の大切さや自然と経営者として成長していくすがたを私は数多く見ています。
リフォーム事業は地域密着型のサービス業ですから売上拡大の際には市場を拡大するために「複数店舗戦略」がどうしても必要です。複数店舗戦略のためには店長候補の育成といった高度な人材育成という側面も必要になります。
有力店の経営者は天性の才があるというよりも、誰しも経験するこの壁を自ら乗り越えてきた方が多いようです。彼らはヒトが育たない、すぐ辞めてしまうという、ヒトの問題に直面しても、一人であれこれ悩まずに、この分野についても学習を怠りません。デールカーネギーをはじめ数多くの書籍により独学は十分に可能ですし、指導者やセミナーも多数ありますので、リーダーシップ、モチベーション管理、人材育成、行動管理、労務管理、コーチング等についても積極的に学習することで、ヒトの問題もその他の問題と同じく、ある程度は乗り越えられる問題です。 |
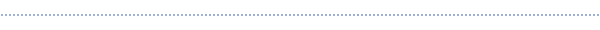 |
成功している事例はごくわずかですが、職人さんや下請業者を営業戦力化できれば鬼に金棒。
|
|
A社には営業マンが一人もいませんが、リピートと顧客紹介だけで年商8億を毎年コンスタントにあげています。A社の特徴は直の職人と下請業者の接客・マナーがずばねけてハイレベルである点です。例えば私のように顧客ではない業者が会社に訪問した際にも、受付嬢ではなく、ニッカボッカ姿の職人さんが「今日も暑いですね」と満面の笑みをたたえてお茶を出してくれます。工事後に顧客に出す御礼状も職人さんたちがすべて手書きで書いていますし、現場近隣への挨拶訪問も職人さんたちが行います。
顧客の立場で言うと、営業マンが丁寧なのはあたりまえですが、現場の職人さんがそれにもまして感じが良い対応を行えばまさに「鬼に金棒」です。職人さんの顧客対応がうまくないために工事中に施主様にストレスがたまり、その職人さんとは関係ないささいなミスでそのストレスが爆発してしまい、大きなクレームになることはリフォーム業者であれば一度は経験されることと思います。
A社の場合は確かに年商規模が大きいため、下請業者がすべて専属である点や、新規開拓が紹介のみなので高い成長率は期待できない点、職人さんのトレーニングに時間やかなりの手間がかかるため、職人さんの増員や絶対的施工量におのずと限界があるなどの問題点もありますが、この手法を実際に実現して成功を納めているいるリフォーム会社があることは事実です。 |
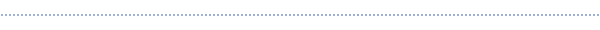 |
「将来のビジョン」と「数字による段階的な目標管理」が営業スタッフの成長を促す
|
|
営業マンが育たないという悩みを多くのリフォーム経営者からお聞きします。多くのリフォーム経営者はトップ営業マンをかねています。仮に倒産してしまえば自分がすべての責任を負いますからその「危機感」が経営者をトップ営業マンにしています。ただこの危機意識をサラリーマンである営業マンに共有させることは難しいと思います。哲学者ピタゴラス曰く「人は必要に迫られるとすぐに実力を発揮する」という名言にあるとおり、精神力の大切さを強調していました。
優れたリフォーム経営者は「ビジョン」と「数字による目標管理」を使って営業マンを育てます。決して「歩合制」や「ノルマ」を推奨しているわけではありませんし。これらの手法はすでに時代の本流からははずれています。
社員にはいろいろなタイプがいますが、例えば「プロ野球選手」になりたいようなリフォームとはかけ離れた具体的な夢やビジョンを追いかけているタイプの人がリフォーム業界に入ってこないでしょう。「この仕事がやりたい」とか「将来は自分でリフォーム会社をやりたい」「自分の経験を生かして今よりよい給料が欲しい」とかどちらかというと願望に近い場合が多いと思います。それらのビジョンは強弱の差はあれ、誰でももっていると思います。
社員が自分自身のビジョンをおいかけるのは「個人」の自由ですが、社員が給料をもらっている以上「組織」の目標に貢献してもらう必要があります。これが「目標管理」です。
「個人」のビジョンと「組織」の目標を線で結んであげるのが経営者が営業マンを成長させる大きなポイントです。個人の「ビジョン」を実現するために、この会社にいる限りは短期的に(段階的に)この数値(通常は粗利益)をこなしてくれという経営者と社員の約束です。
段階的な目標管理を行うことで営業マンが小さな「成功体験」を積み重ねると、営業マンは多くの場合自ら自然と「トップ営業マン」への道を歩き始めます。(自分で設定した)目標をクリアする喜びがその人の持っている「営業マン」としての資質を大きく開花させることがよくあります。そして自分のもっていた能力が開花するとそこで生まれた「アイデンテティ(自分のいるべき場所)」が自信につながり、将来の幹部候補生や店長候補になるケースも多くあります。
実際にそれまで自己のアイデンテティが築けずにいた人材が、リフォーム業界に入り、優秀な経営者のもとで成長することで、いままで気付かなかった能力に目覚め、トップ営業マンや店長などの幹部に短期間で自己変革していくケースを私自身何度も目にしてきました。
毎日のように目標への足跡や実績を数値で確認することで、目標への意欲は持続され、常に数字を意識した行動をとるようになります。具体的には今月の数値が足りなければ、なんとかして目標数値をクリアしたいという気持ちが「熱意」や「努力」や「アイディア」ひいては自己成長につながります。
A社では粗利益による目標管理を行っていますが、具体的には社長が毎朝かかさず、ひとりひとりの現在の実績数値と目標までの数値や達成率を壁に張り出しています。営業マンは毎朝、自分の数値を見てから席につき、仕事をはじめます。 |
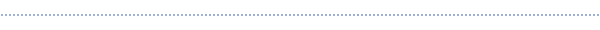 |
成長を持続したいなら変化を恐れずに、変化に挑戦し、変わりつづけなければならない
|
|
弊社のユーザーにはリフォーム事業に参入した直後の会社から年商5億超の会社までありますが、年商規模の各段階で経営スタイルや抱えている問題点はまったく異なります。
例えば年商5~7000万位まででしたら一人でも十分可能ですので、リフォーム事業そのものの運営ノウハウを構築する時期です。この段階ではマンパワーが主体ですので単純にその人の実務能力が問われます。
次に年商1億を超えるためには2~3人のスタッフを使わなければなりませんから経営者や責任者自らが、プレイングマネージャーとして現場をこなしながら、人材育成を図らなければなりません。良くある例としては、この段階で即戦力増強ということで経験者を増やした場合、その経験者が自社の「社風」や「やり方」とのギャップに悩んだり、定着しない、社内の雰囲気が悪くなるなど難航することもありますので相応の舵取り能力が必要です。
年商2億を超えるためには例えば「水廻り主体」から「総合リフォーム」に扱い部位を大幅に拡大しなければ難しく、スタッフも5~6人以上必要ですので、経営者や責任者の経営管理・マーケティング業務が増えて、現場の多くの業務を人に任せなければなりませんから相応の「任せるノウハウ」が必要です。経験やノウハウの浅い人材に業務を任せることでどうしてもクレームが増えて、成長への意欲が薄れ、成長が鈍化してしまのはこの時期が比較的多いようです。
年商5億を超えても成長を維持するためには経営者や責任者の経営管理・マーケティング業務に専念しなければ難しいと思います。現場レベルの責任者は右腕を別に設けて組織として管理するノウハウが必要になります。
このように売上の成長とともに経営スタイルや経営組織は常に変わりつづけなければ次の段階に進むのは難しいと言わざる負えません。経営者は自ら変革するのは当然として、自社が目指す方向と理念を具体的に社員に提示し、社員に自ら自己変革を促す能力が必要になります。
成功店の経営者に共通することは彼らは年齢にかかわらず「若々しい」という点です。仕事に限らず若さを保つ秘訣は「新しいことにチャレンジすること」とは昔から言われています。変化の激しい時代や変化の激しい市場に生き残るためには,変化を恐れず、変化に挑戦する姿勢がもっとも大切なのかもしれません。 |