| ���t�H�[�������@�Ǝ�E�Ƒԕʂ̐����̃|�C���g |
 |
�ʍe�ł��ӂꂽ�Ƃ���A���t�H�[�����Ƃ́u�����v�ւ̓��͖����ɂ���Ǝv���܂����A�u���s�v�ɂ͂����炩�ɋ��ʓ_������܂��B
���͖^�Z��ݔ���Ђ̃��t�H�[�����Ǝx���̕����ɋΖ����Ă���������30�N�ȏ�A���t�H�[�����ƂɎ��g�ފ�Ƃ̗l�X�Ȑ��������Ă��܂������A�����炩�ɓ����悤�Ȍ����Ŗ��N���N�����̉�Ђ����t�H�[���s�ꂩ�瓑������Ă��܂��B
���鎸�s�������t�H�[����Ђ͋ɒ[�ɑ��Ђ́u�^���v��������P�[�X������܂����B10�N�A20�N�������Ă��琬������]�T������Ȃ�͂��߂���I���W�i���e�B��Nj����Ă������Ƃ��悢�Ǝv���܂��B
�������A�V�K���Ƃ͑����̏ꍇ��2�A3�N�Ō��ʂ����߂��܂��B���̃C�`���[�ł�����{�Ƃ���o�b�^�[�̂܂˂���n�܂�A�A�����W���J��Ԃ����ƂŎ����̂��̂ɂ��Ă������̂͗L���Șb�ł��B
�����ł́A�킽�����ߋ�30�N�ԂŖʒk�������t�H�[�����3000�Ђ̒�����A���t�H�[�����ƂɎQ�����邱�Ƃ������Ǝ�E�ƑԕʂɁA���Ɏ��s�̓T�^�I�Ȏ�����܂Ƃ߂Ă݂܂����B |
|
| �ݔ��E�����Ƃ��烊�t�H�[���ɐi�o����ꍇ |
�ݔ��E�����Ƃ́u������Ёv�����t�H�[�����Ƃɖ{�i�I�ɐi�o���鎞�̍ő�̋��݂͏C���ڋq�̑����ł��傤�B�܂������̐V�K�n�ƂłȂ���Ό��݂̃X�g�����O�|�C���g�����p���ĐV���Ȑ�����ڎw���̂������ł��B
�C���ڋq�𐔑������u������Ёv�͐��ݓI�Ƀ��t�H�[�����Ƃɐ�������傫�Ȏ��������łɎ����Ă���Ǝv���܂��B
�܂��������Œ����ԃG���h���[�U�[�Ƃ�����葱���A���ߍׂ��Ȃ��q�l�̗v�]�ɑΉ����Ă������Ƃ́A�{���ɑ傫�ȕ���ƂȂ�܂��B��������Q�����Ă����ꍇ�A�G���h���[�U�[�Ə��ɊW��z�����ɂƂ�����邱�Ƃ��悭����܂��B
�ݔ��E�����Ƃ́u������Ёv�����t�H�[�����Ƃɖ{�i�I�ɐi�o����ꍇ�̉ۑ���l���Ă݂܂��傤�B
�V�K�ڋq�̊J�����������ł����A�ނ���ڋq�Ǘ��\�t�g���t�����p���āAOB�q�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����𖧂ɂ��A�u����蒆�S���t�H�[���v�͈̔͂ŋ�̓I�ɂ́A���ɒP���̍����L�b�`���Ȃǂ�ϋɓI�Ɉ������Ƃŏ������ł���ė͂��������A���ϒP�����A�b�v���AOB�q�����߂�S�Ă̕��ʂ̃��t�H�[����ϋɓI�Ɏ��g��ł����K�v������Ǝv���܂��B
�g�C���͋�������ǁA�L�b�`���͂ǂ����E�E�E�Ƃ����悤�ȋ�蕔�ʂ�i�K�I�ɖ������A�P���̍����L�b�`���◁�����t�H�[���ɂ͓��ɒ��͂��A�����ȊO�̕��ʂ������ÂϋɓI�ɐ�������悤�ȑ̐�����邱�ƂŁA�Œ�q�̃��s�[�g�𑝂₵�A�n���ɂǂ����Ă��K�v�ȉ�ЂɂȂ邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B |
�@ |
 |
|
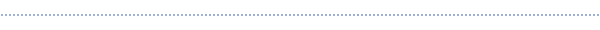 |
�C���q�͂����瑽���Ă����t�H�[�����Ɛ�p�̌ڋq�Ǘ��\�t�g�Ȃǂł�����ƊǗ�����Ă��Ȃ�����̋��݂����������Ƃ͂ł��܂���B���Ѓ\�t�g�̐V���ȃ��[�U�[��Ƃł��C���q�𒆐S�ɐ��猏�̌ڋq�f�[�^�x�[�X������Ђ������Ă��܂��B
�����̌ڋq�ɑ��A�h�������A�J��Ԃ��A�J��Ԃ��A�u�C����Ёv�̃C���[�W���u���t�H�[����Ёv�̃C���[�W�ɍ��߂Ă������߂̏�M���_�C���N�g���[����t�H�[�����k���V���[�c�[�����w�o�X�c�A�[���̃C�x���g�Ōp�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�u�C����Ёv�̃C���[�W�̂܂܂ł͒P���̍��������̈����������̂��̂��͎��ɂ����Ȃ�Ǝv���܂��B
���������������߂Ȃ�����A�ڋq�ւ̏�M���p�����邱�ƂŌi�C�����ɍ��E����ɂ����A���s�[�g�����������߁A�e���v�̍����A�n���ɍ��t�����D�lj�ЂɂȂ邱�Ƃ��\���ɉ\�Ǝv���܂��B |
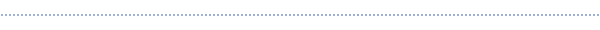 |
�u����蒆�S���t�H�[���v�ł͂P�X�܂Ŕ���0.8�`1.5�����x��˔j�����Ƃ��ɁA�傫�ȕǂɂ������Ђ������悤�ł��B���̕ǂ͎�Ɂu�v���[���[�v����u�}�l�[�W���[�ցv�̕ǂƌ����Ă��܂��B�u�v���[���[�v�Ƃ͌�������Ȃ��S���҂Łu�}�l�[�W���[�v�Ƃ͌o�c�Ǘ��S�ʂ̒S���҂ł��B�����̐����X�͔���̐����ƂƂ��ɎЈ��������܂��̂ŁA�u�v���[���[�v����u�}�l�[�W���[�ցv���ȕϊv���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���ۂɂ͂��̒��ԂŁu�v���C���O�}�l�[�W���[�v�̎������ǂ����邩���傫�ȉۑ�ł��B�u�v���C���O�}�l�[�W���[�v�̎����Œ���Ă����Ђ����Ȃ葽����ۂł��B
������̕ǂ́u����胊�t�H�[���v����u�������t�H�[���v�ւ̕ǂł��B�ݔ��E�����Ƃ̏ꍇ�A���̕ǂ��傫�ȉۑ�ƂȂ鎖�������悤�ł��B
���̌o���ł́A��Ђ��ۗL���Ă���H���̋Z�p�Ȃǂ͂��܂�W�Ȃ��A�O�q�́u�}�l�[�W���[�ցv�̕ǂ������Ђ́u�������t�H�[���v�̕ǂ��Ȃ�Ȃ������Ă��܂����Ƃ������悤�Ɏv���܂��B���̉ߒ��œ��z�m�Ȃǂ̎擾��ڎw�����Ƃ��������̎��Ⴊ����܂��B�u�������t�H�[���v�ւ̕ǂ����z������Ƃ͔N��3�`5�����x�́u�n���ԓX�v�ɂȂ鎖�Ⴊ�����悤�ł��B |
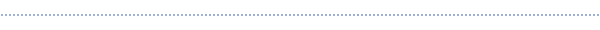 |
�t�ɐݔ��E�����H���X�ł����Ă��H���X�̉�����������d�������C���Ɩ��������u����Ёv�̓G���h���[�U�[�Ƃ̍D���x�̍����A�v���[�`��ڋq�J�̂��̂�����������ȃP�[�X�������A��풆�̉�Ђ������͎̂����ł��B
�u����Ёv�ɂ͓�̑傫�ȃn�[�h��������܂��B��͌ڋq���u�Ǝҁv����u�G���h���[�U�[�v�ɕς��Ƃ����n�[�h���B������͍��܂Ō��肵�����Ӑ�i�����⌳���j����J��Ԃ��������Ă������ߎ��g�ނ��Ƃ������Ȃ������u�V�K�ڋq�̊J��v�Ƃ����n�[�h���ł��B���̓�̃n�[�h�������z���邽�߂ɕK�v�Ȃ��͈̂ꌾ�Ō����Ɓu�N�ƉƐ��_�v��������܂���B
���̂悤�ȉ�Ђ͎����葁���A�Ⴆ���[�J�[�̃`�F�[���X�ɉ������邱�ƂŎ�_���������悤�Ƃ���ꍇ�������悤�ł����A���[�J�[�`�F�[���ɉ������������ł́A�����ڂ̃C���[�W�͕ς���Ă��A��Ђ̖{���͕ς��f�����Ȃ����Ƃ�����������܂���B�܂�2020�N���݁A���t�H�[�����Ƃɒ��͂��Ă���Z��ݔ���Ђ͈ꎞ�����������Ă��܂��B
�O���̃f�U�C����ЂȂǂ��g���A��Ƃ̃C���[�W���悯��悢�قǁA�Ј��̌��t�����≞�A���t�H�[�����Ƃ��̂��̂̐i�ߕ��̏n���x�ȂǂŁA���q�l���������肵�Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B |
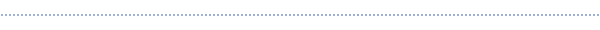 |
�u����Ёv�ŏZ��t�H�[�����Ƃɐ������Ă����Ђ̓g�b�v�����悵�Ă��܂܂ł̎Е���ϊv���Ă��܂��B���ꂪ�ł��Ȃ�����[�J�[�̃`�F�[���ɉ���������A�R�[�f�B�l�[�^�̏������̗p������A�V���[���[����Ƃ����������̕ω��ł͂��̍����đ傫�ȕǂ����z���邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B�������������Ă������t�H�[�����ƎQ���̎��s��͂��̎Е��̈Ⴂ�����z���邱�Ƃ��ł��Ȃ�������Ђ����������߂܂��B
�������u����Ёv�Ő������Ă���P�[�X������܂��B�Վ�̑��q�ɑS�ʓI�Ɍ����Ϗ����A�ʉ�ЂȂǂ�����Ă���Όo�c�̏C�s�������Ă���悤�ȏꍇ�������Ǝv���܂��B���̂悤�ɐ�Ɏ��s��������������Ȃ��A����̂����łȂ���[������ڋq���J�A��������͓̂���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B�V���[���[��������āA�c�U����̕�����ӔC�҂ɂ��A�e��Ђ���̏Љ�Ŕ�����U���Ă���悤�Ȋ��Ő������铹�͂���߂Č������Ǝ��͎v���܂��B |
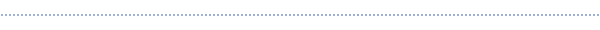 |